 |
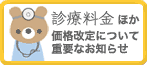 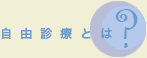 |
 生薬の効能についての注意点 生薬の効能についての注意点生薬を一つずつ取り上げて、その効能を簡単に述べていきたいと思いますが、最初に注意しておくことがあります。 ここで記載する知見は私の父(故遠田裕政)が提唱した『近代漢方』に基づいています。 また、漢方薬は甘草を除いてはほとんどが単品で使われることはなく、他の生薬と一緒になって使用されておりますので、その生薬の組み合わせで構成される漢方薬の使われ方や伝来の条文から推定されたものです。 人間の生体を構成する物質でもっとも多いのは水です。およそ体重の70%を占めていて、そのうち約50%が細胞内液、約15%が細胞外液、約5%が血液であると言われています。 したがって、この水の生体内での有り様が生命個体の存在状態を大きく規定していると推定されます。 生命個体の水の出入りを考えると、摂取は飲水という1方法ですが、排出は発汗、嘔吐、下痢、利尿の4方法があり、嘔吐と下痢は胃腸管を通じて排出するものなので、嘔吐は下痢の一亜型と考え、結局排出方法としては下記になります。 ・皮膚を通じての排出(発汗) ・胃腸管を通じての排出(嘔吐 下痢) ・腎を通じての排出(利尿) 飲水によって取り込まれた水に様々な電解質や栄養素などを溶かし込み、血液その他の体液を構成し、不要なものを上記3方法によって身体から排出しながら、個体の状態を一定に保っていると考えられます。 漢方薬は上記の3つの働きに作用して、その生体のバランスを助ける働きがあると経験的に知られていったようです(もちろん昔は臓器のことは知られていませんでしたので、汗がでる、嘔吐する、下痢する、おしっこがでるというような反応を見ていたのだと思います)。つまり ・皮膚を通じての排出(発汗)の促進あるいは抑制 ・胃腸管を通じての排出(嘔吐、下痢)の促進あるいは抑制 ・腎を通じての排出(利尿)の促進あるいは抑制 各生薬の基本的な反応も上記のいずれかに属しています。 生薬の数が増すほど上記の働きが拮抗されながらうまく調和して、一定の働きとなり、また生薬独自の作用も加味されて、ある病態を改善するのにふさわしい治療効果があらわれてくると推定されるのです。 ※以下、生薬名をクリックしてご覧ください。
|
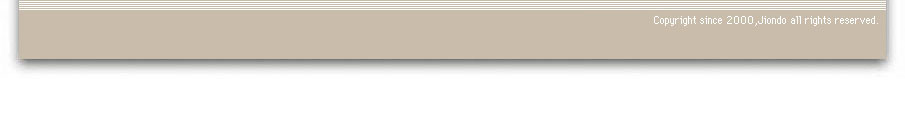 |